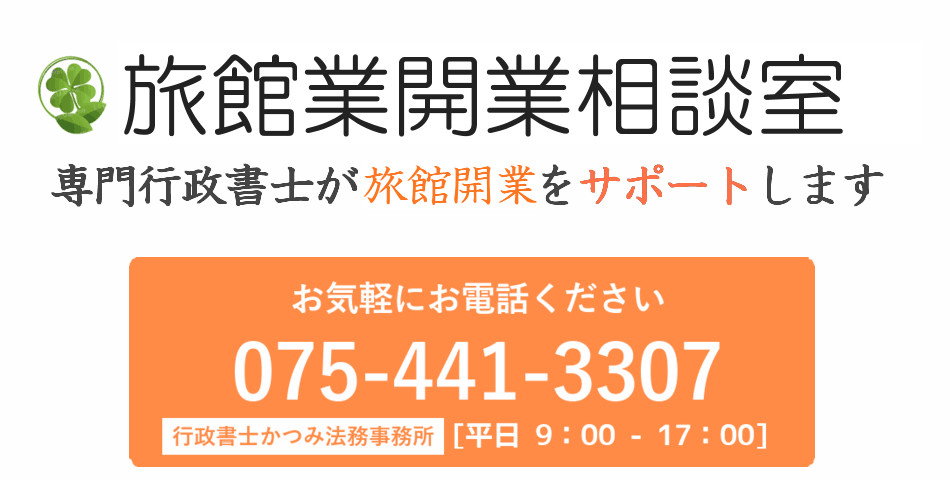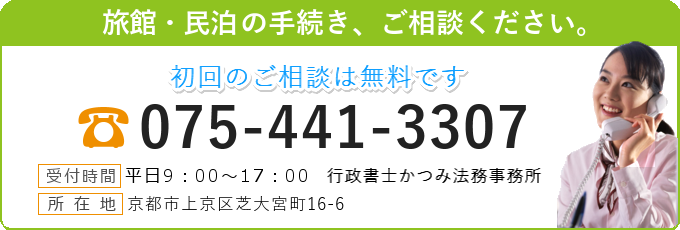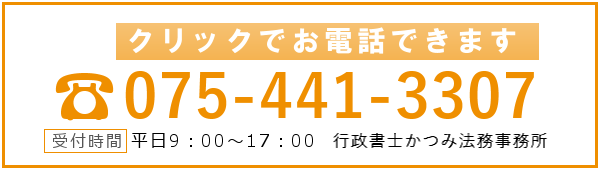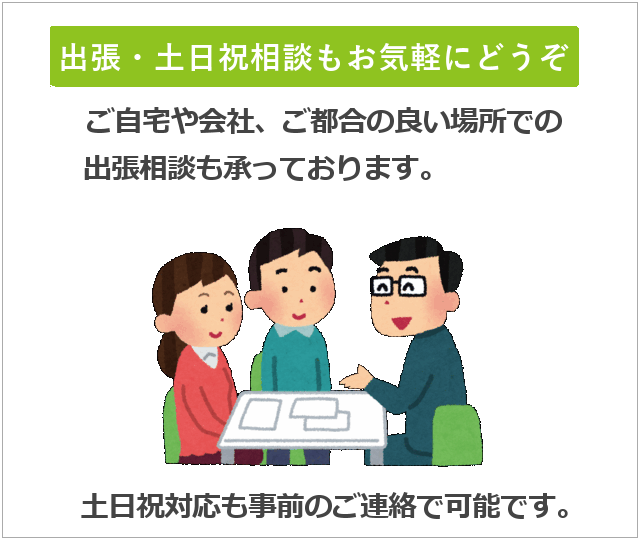住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
ガイドラインの重要性
2017年12月に住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等をとりまとめた「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」が発表されました。
「解釈、留意事項等をとりまとめ」とだけ聞くとわかりにくいかもしれませんが、今後はこのガイドラインに沿って住宅宿泊事業法は施行・運用されることになり、これをよく読めば民泊新法でできること・できないことをおおよそ理解することができるといえるのです。
実際のところ、法律そのものには解釈の余地を残すためにある程度抽象的な文言が使用されている事が多く、そのため法律だけでは実際にどうなるのかわからない部分も多くあります。住宅宿泊事業法の場合、最終的なところは各自治体の条例で決まりますが、自治体の条例も基本的にはこのガイドラインから逸脱したものになることは考えにくいといえます。
最重要法第2条「住宅」の定義とは
ガイドラインにおける最重要部分は何といっても法第2条「住宅」の定義です。
特区民泊と民泊新法でも記載しましたが、この定義によってどのような建物で民泊を運営できるのかが決まってしまうからです。
法第2条の条文だけでは一戸建て住宅のみ指すのかそれともマンションやあるいは事業用のビル等でも該当する場合があるのかはわかりませんでした。実際のところ特区民泊が伸び悩んでいると思われる理由の一つとして特区民泊においてはこの建物用途が「住宅・共同住宅」用途である必要があったため、「住宅・共同住宅」用途に変更できない古い事務所ビルの経営者の方などが断念せざるを得ない事情があったことがあります。
もし今回の住宅宿泊事業法(民泊新法)の住宅の定義についてもこれが踏襲されるとしたら(条文を読むだけだとそのような可能性の方が高いように思われた)、また対象となる建物が大幅に限定されることになると思われました。
今回のガイドラインには法第2条の「住宅」の定義について
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋である。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しない。当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届出をする場合には、当該家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しているものとして差し支えない。
居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しない。
としており、また留意事項には
一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断する。
住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2条柱書において本法における住宅の対象から除外している。
上記からは建物の用途に関わらず、人が継続して居住していれば良いように読めます。国土交通省に確認したところ、やはり建物の用途については問わない、との回答でした。
これが意味するところは民家や賃貸マンションではなく貸事務所ビルなどであってもオーナーが居住している階などであれば用途変更することなく民泊として使用できる可能性があるということになります。
その他の重要ポイントは
その他の重要ポイントの一つとして設備要件に関する考え方があります。
旅館業許可において悩まされるポイントの一つが水回りですが、ガイドラインには
「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けら れている必要はない。同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることは差し支えない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する。
これらの設備は必ずしも独立しているものである必要はなく、例えば、いわゆる3点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする。
これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足りる。例えば浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式等の別は問わない。
上記のように浴槽を不要とするなど予想よりも緩やかに思える条件となっており、実施できる期間の制限こそあるものの、設備投資額としては旅館業許可よりも割安感がかなりあると思えますのでこちらを選択する方もかなり多くなりそうです。